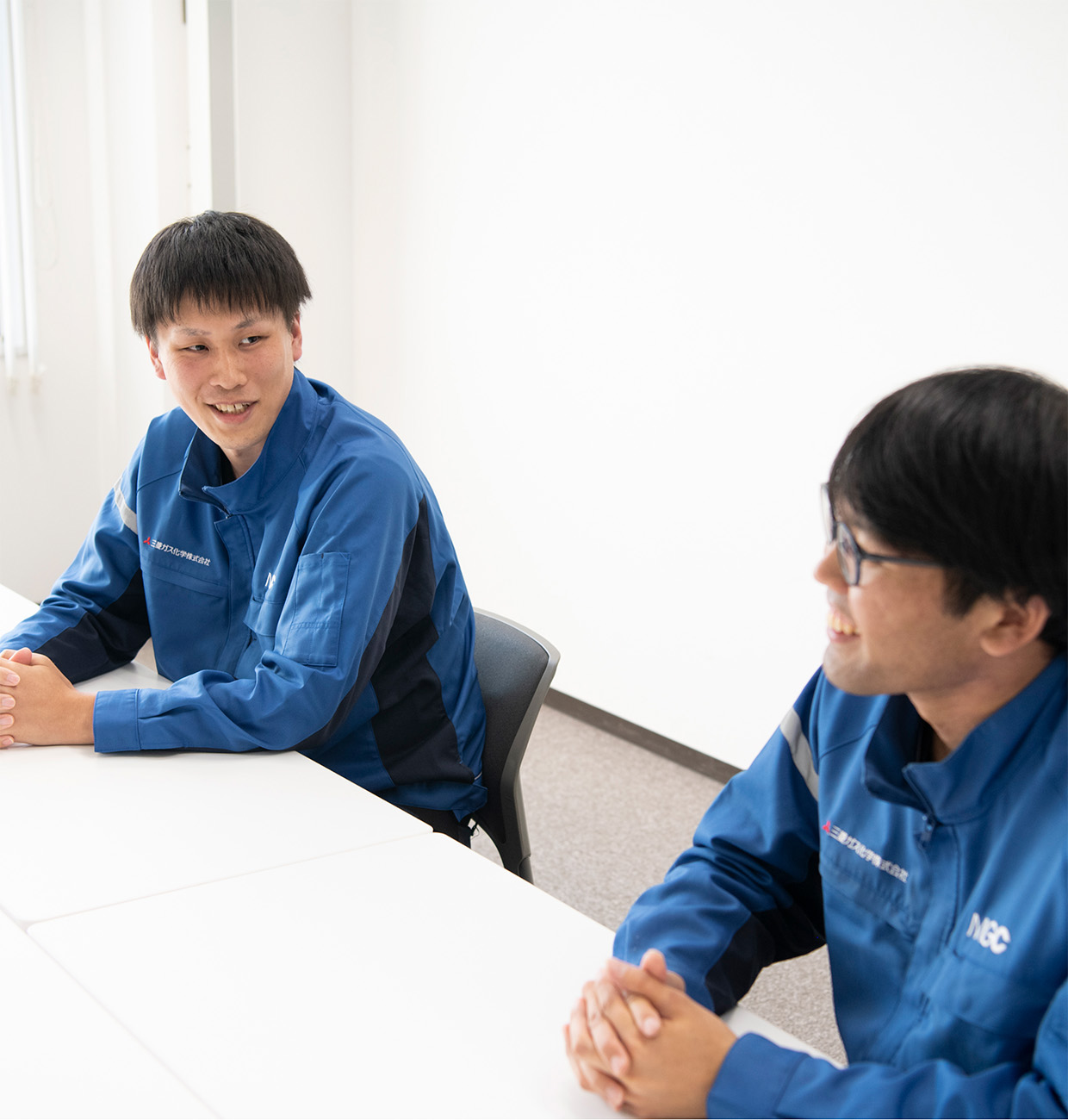機電系対談


電気・計装のプロとして
進化する技術に対応し
機電系社員の価値をさらに高める
進化する技術に対応し
機電系社員の価値をさらに高める
-
Hさん(左)新潟工場 工務部理工学研究科
電装グループ
電子情報工学専攻 -
Tさん(右)新潟工場 工務部先端技術科学教育部
電装グループ
システム創生工学専攻
電気電子創生工学コース
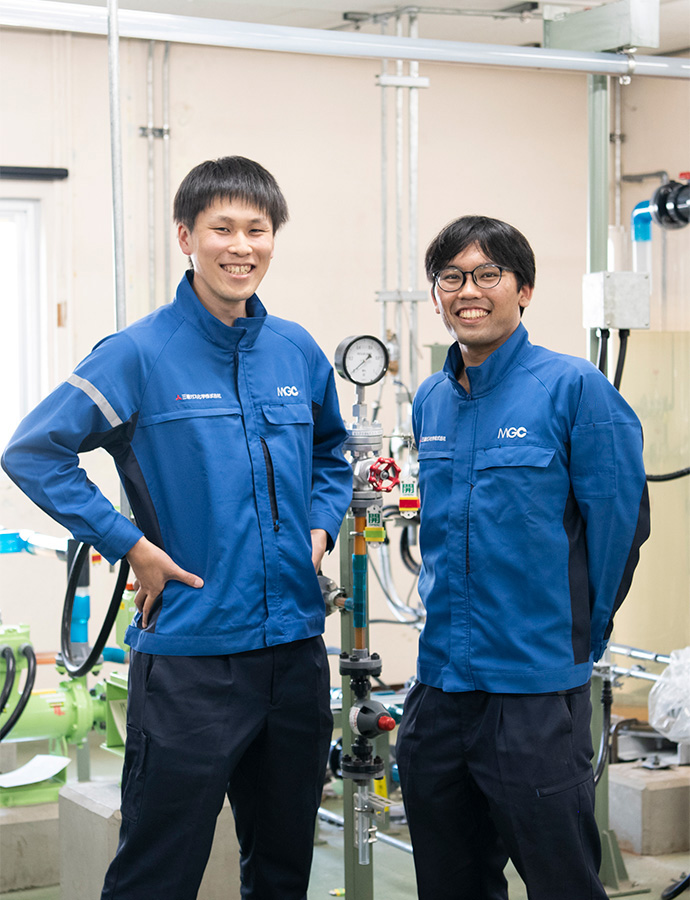
-
機電系の技術者が活躍するフィールドがあると感じた
 Hさん
Hさん- 就職活動のときに自己分析をしてみたら、自分が目立つのではなくチームをサポートするほうが合っているという結論になりました。高校までやっていたサッカーでもゴールキーパーでしたから。そこで、大学院で研究していた半導体の知見を電機メーカーなどの研究職で活かすのではなく、別の切り口で就職先を探し始めたのです。
 Tさん
Tさん- 私はある機電系学生向けのイベントでMGCの存在を知ったのですが、説明だけでは正直イメージがつかめませんでした。でもその後、MGC水島工場のインターンシップに友人と参加。社員と一緒に仕事を体験するプログラムを通じて一気に興味が湧きましたね。
 Hさん
Hさん- そういう機会があったんだね。私の場合は製造業の設備管理で「生産活動の根幹を支える業務」があると知り、さらに調べていって、素材から最終製品まで幅広く事業展開をしているMGCにたどり着きました。OBの社員にいろいろな話を聞いて、工場内では数少ない機電系のスペシャリストとして、計画立案から装置稼働の支援まで幅広く携われることがわかった。それでMGCに決めたのです。
 Tさん
Tさん- 私もインターンシップで、「腐食しやすい物質を扱っていることからプラントの保守頻度が高い」という話を聞き、機電系業務の責任の重さ、やりがいの大きさに魅力を感じました。一応、他の業種・メーカーも受けましたが、やはりMGCで働きたいと思い、入社を決めています。
 計装・電気の業務を通してトラブルの予防に向き合う
計装・電気の業務を通してトラブルの予防に向き合う Hさん
Hさん- そして私もTさんも入社以来、新潟工場の工務部 電装グループに勤務しています。
 Tさん
Tさん- グループは同じですが、担当する領域が分かれていますね。
 Hさん
Hさん- 私が計装設備の担当で、Tさんは計装設備・電気設備両方を見るチーム内で主に電気設備を担当している。
 Tさん
Tさん- MMA(メタクリル酸メチル)装置のように、計装をHさんが、電気を私が担当しているケースもありますが、基本的に行動は別々ですね。装置の何をチェックしなければならないかによって、出番が違いますから。
 Hさん
Hさん- それぞれ別々のミッションも持っているしね。私の場合は、日頃の計装関連の設備管理はもちろんだけれど、ビッグデータを使ったスマートポジショナー(計装弁のバルブ開度を調節する操作器)の導入を進めている。摺動回数や滑らかさなどのデータをもとに判定値を決めて、装置トラブルの予防保全に活用する予定です。
 Tさん
Tさん- 私は"TZ越後屋"というワーキンググループに入って、電動機の故障を未然に防ぐ新技術の導入を進めているところです。設備などで使われる電動機などは、製造課から相談を受けて整備に出すのが基本ですが、電動機がないと装置自体を停止しなければなりません。相談を受ける前に診断し、大規模な定期修繕の機会に整備に出しておけば、ふだんの稼働に影響が出ませんから。
 Hさん
Hさん- じゃあ、二人とも「予防」という観点では共通のミッションを持っているんだね。

-
停電作業や海外拠点の支援で技術者としての成長を感じた
 Hさん
Hさん- 定期修繕といえば、Tさんは今年の定期修繕で「停電作業」を担当したね。2年に1回の作業だから、大変だったでしょう。
 Tさん
Tさん- はい。まず事前に当日のスケジュールを組み、"◯時◯分に何をやるか"を細かく決めて、停電前確認会議で上司と工事業者の方々と打ち合わせをします。当日はもう一度関係者がスケジュールを確認し、電気主任技術者の立ち会いのもとブレーカーを落とす。検電で安全を確認して、業者に作業をお願いして、作業後は工具などの忘れ物がないか確認して……。
 Hさん
Hさん- 工具などがあると、通電したときに大事故になるからね。
 Tさん
Tさん- その工程を複数ある担当装置ごとにくり返すというのは、良い経験になりました。Hさんは最近メタノールの海外拠点に行きましたよね。いかがでしたか。
 Hさん
Hさん- DCS(分散制御システム)の更新とボイラーの建設の支援でベネズエラに1ヵ月行ってきました。現地での会話は基本スペイン語でほとんどわからなかったけど、しっかりとした技術があれば支援できることがわかった。現地の技術者たちもプロ意識が強いのですぐに議論がヒートアップするけれど、その結果良い方向に進むのを見て、技術に加えて熱意も大事だと実感したね。
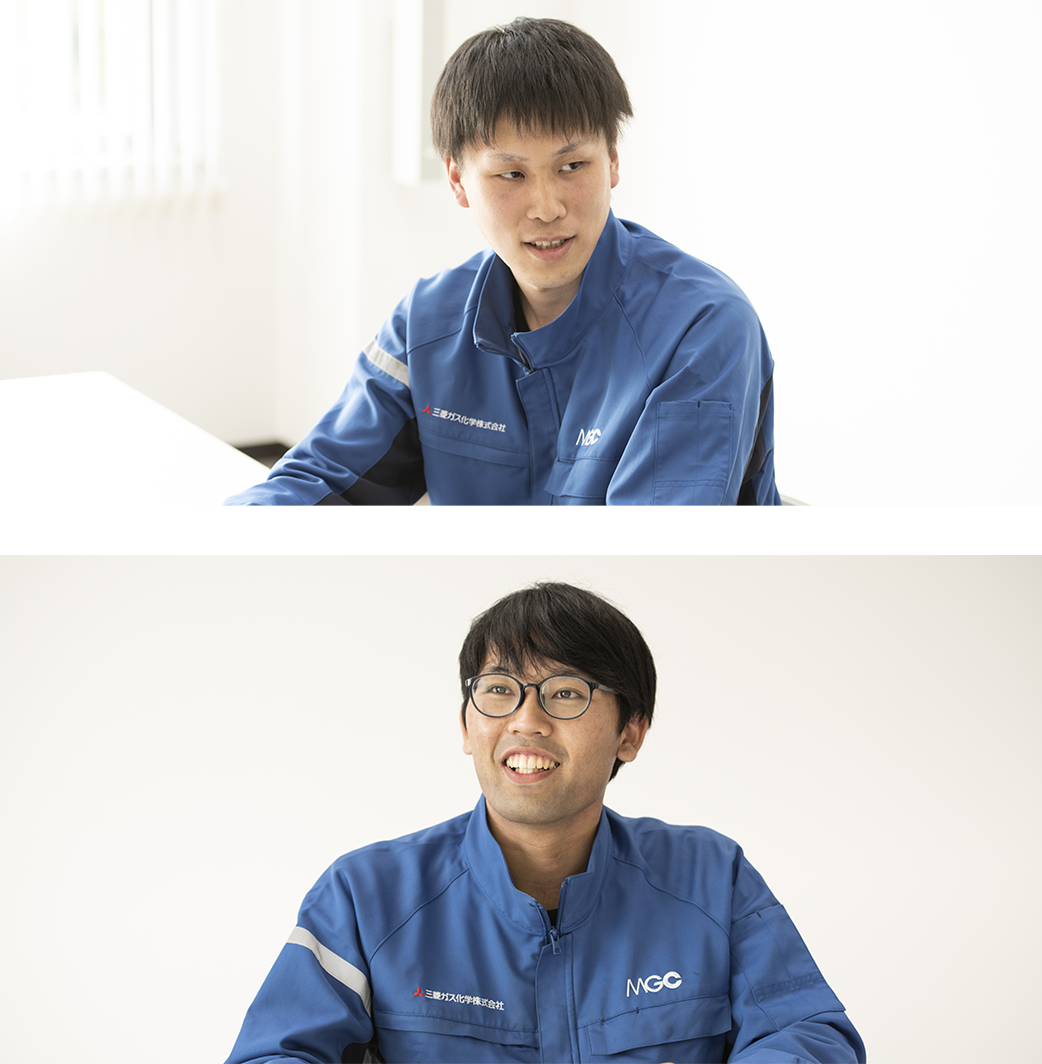 どんな問題にも難なく対応する技術と熱意を持った技術者に
どんな問題にも難なく対応する技術と熱意を持った技術者に Tさん
Tさん- 海外拠点の支援は、私もいつか行ってみたいですね。それにはまず、今担当している電気設備に加えて計装設備についても詳しくなって、どのようなトラブルも難なく解決できる技術者にならないと。その対応力と、あとは語学力でしょうか。
 Hさん
Hさん- 語学力があるに越したことはないけれど、経験上、やはり技術と熱意だと思う。AIやIoTなどの技術が進歩していくことで、人がやらなければならない範囲は狭まっていく。だからこそ、取って代わられることのない技術と、人が持つ熱意は大事になるね。私は装置の建設プロジェクトに一から携わるチャンスが欲しい。様々なスペシャリストと協力して建設に取り組むことで、柔軟な発想力や多様な視点を手に入れたいと考えている。
 Tさん
Tさん- こういう話はなかなかしないですね、同じ電装グループなのに。
 Hさん
Hさん- お互いに広い工場を自転車で走り回っているからね。こういう機会があって良かった。
 Tさん
Tさん- でも私はHさんの趣味がバスケットボールだって知ってますよ。ちなみに私の趣味はゴルフです。
 Hさん
Hさん- 一緒にできなくて残念。そういえばTさんはコロナ禍の入社だったから、歓迎会をしていないですよね。いずれチャンスが来たら、歓迎会を企画しますよ。そのときじっくり話しましょう。